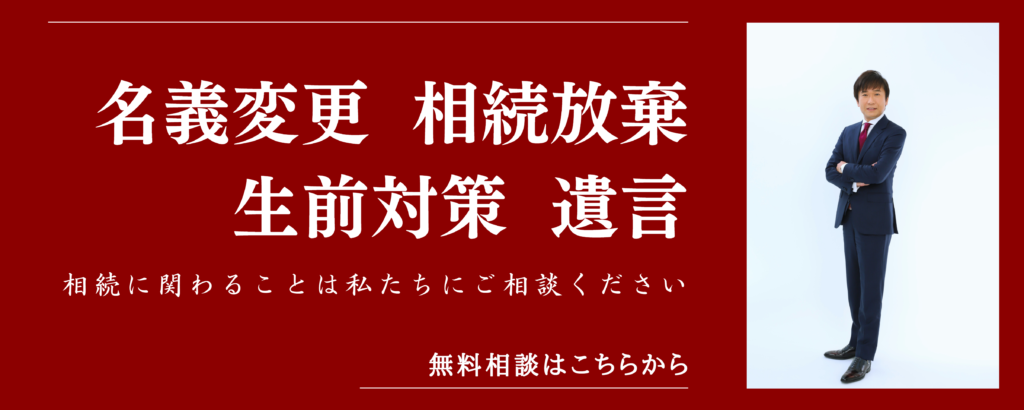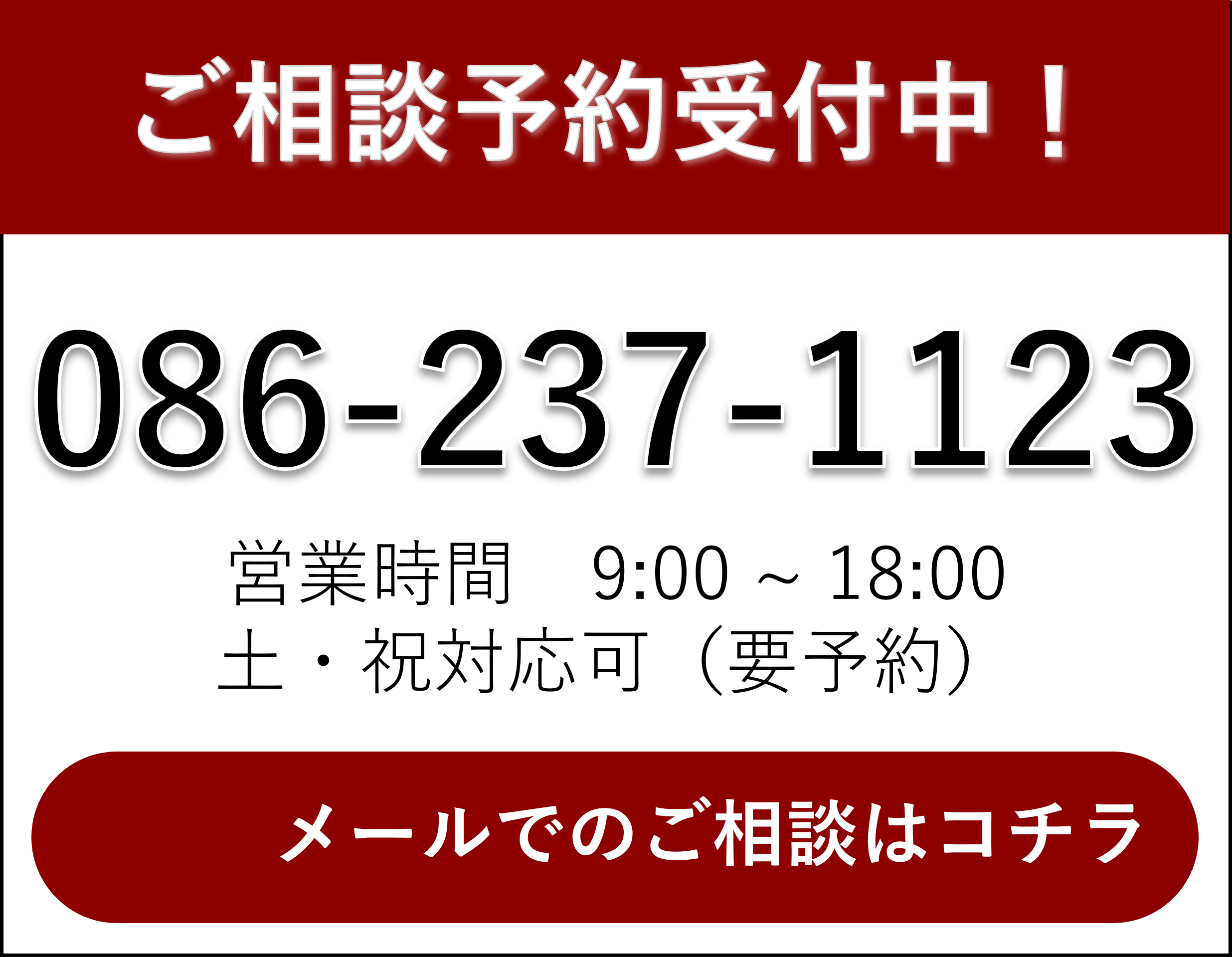ここでは、生前贈与についてご説明します。
●暦年贈与や連年贈与について
●夫婦間の贈与について
詳しく解説していきます。
暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、
「相続税よりも税率が高い」という印象をもたれている人が多いようです。
確かに、税率は比較的に高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかけることで、
節税の効果も出てきます。
例えば、子供が二人いて、20年かけて、毎年限度額の110万円まで贈与をすれば、
4,400万円までの財産は税金がかからないのです。
しかし、最初から4,400万円の贈与をする意図であったと、税務署に判断されると、
初年度に全体を一体として贈与税の課税がされるため、注意が必要です。
これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率がとても高いので、
多額の税額が課されてしまいます。
連年贈与とみなされないためには
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、
連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そうするためには下記のことを注意して、贈与を進める必要があります。
・最も典型的な例が、110万円を超える贈与をして敢えて贈与税申告をすること
・贈与契約書を贈与の都度作成すること
・贈与を受ける方ご本人の口座に振り込むなどの方法により記録を残すこと
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等をすること
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
財産が多い方、贈与に年数をかけていられない方は、年110万円の贈与では、
足りないと思われるかもしれません。
例えば、相続税の税率が50%と予想されるような場合に、年間500万円の贈与を行うと
贈与税は約50万円で実質10%の税負担となります。
つまり、相続まで待てば50%もの相続税がかかってしまうところを、
生前贈与により10%の贈与税の負担で済ませてしまうことができます。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、
資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、
個別に考えていく必要があります。
当センターでご紹介いたしますので、お気軽にお問合せください。
相続時精算課税とは

※2010年は従来の非課税枠2500万円に加えて特別控除枠が1500万円に
拡大されましたので、住宅取得等資金は最大4000万円まで非課税です。
(ただし、4000万円の非課税枠が利用できるのは平成22年限りで、
平成23年は非課税枠が3500万円となる予定です。)
ここでは、相続時精算課税制度の一般的な説明ですので、基本的な非課税枠である
2500万円での表記としております。
相続時精算課税では、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与であれば、
2500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で
控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を
提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、
相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、
その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較
| 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 | |
| 贈与者 | 65歳以上 (住宅取得資金の場合には制限なし) |
年齢制限なし |
| 受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子、もしくは孫) |
年齢制限なし |
|
基礎控除 |
限度額2500万円を複数年にわたって利用 | 年110万円 (毎年利用可) |
|
税率 |
一律20% | 10%~50%(6段階の累進課税) |
| 相続時の取扱い | 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。 | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合
平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上である子が親から
住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか
又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ
2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1500万円の住宅資金特別控除額を
控除することができます。
(なお、特別控除枠は平成23年には、1000万円に縮小されることとなっています。)
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
 贈与を受ける人の条件
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与者の無制限納税義務者であること
 贈与をする人の条件
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
 取得する住宅の条件
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に
建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に
建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、
建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
贈与税額の計算(暦年課税)の特例
平成22年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、住宅資金の非課税枠が1500万円に増額されました(平成23年は、住宅資金の非課税枠は1000万円に縮小される予定です)。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築でも、上記の特例が使われるようになっています。
つまり、1610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1500万円)までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。
この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、期限内に贈与税の申告する必要があります。
 贈与を受ける人の条件
贈与を受ける人の条件
・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円(給与所得の場合は約2280万円)以下
・贈与税の無制限納税義務者であること
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
 贈与をする人の条件
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
 取得する住宅の条件
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に
建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に
建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、
建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
夫婦間の贈与

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2000万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等であること以外に、いくつか条件があります。
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。
または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、 または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記事項証明証
4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。
負担付死因贈与契約

贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。
贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、
贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することが出来ないのが特徴です。
これに対して、実は遺言書は執行者を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する
内容で協議し、合意した場合、無理矢理実行させることは出来ません。
もし、意思を確実に実現したい場合は、死因贈与契約も有効と言えます。
さらに「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、
何らかの義務・負担を強いることです。
贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、
利益を受けるということになります。
具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といった
ケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、
使い勝手の良い制度になっています。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、
契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
契約内容を明確に記載しておくことが大切で、
■贈与の対象資産
■負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、
贈与をする方が撤回することが可能です。
贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが
大切です。
ちなみに、死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。
言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。
贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。
また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。
ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として取り消し・一方的な破棄は不可
となります。
遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合、効力が発生するのですが、
ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。
書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、
遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。
遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
その他のコンテンツ